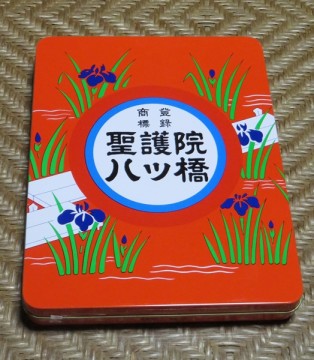聴老(お年寄り&昔の話)
昔の農村の娘さんのこと R君から八ッ橋のお土産。
過日昭和4年生まれのおばあちゃんから娘時代の事をお
聞きした。
その人の父親は病弱なため農作業から身を引いていたら
しい。
家には7反の田があり、仕事は長女のその方が中心にな
って働くことになった。
母親に次々と子供が出来たので自然にそうなった。
小柄だったが、少女時代から牛を使って田を起こし,代掻き
を行い、苗取り、田植え、草刈り、稲刈り、ワラ仕事などみな
行った。
稲刈り後は稲を干すはさ木に上って稲束を受け取り、上ら
ない時は束を竿で刺して持ち上げ、はさ木に上った人に渡
した。
近所や親戚の助けも借りたが、あくまで責任は自分の肩
にあった。
戦時下の村で男たちは次々と出兵し、行き詰まった農家か
ら田を任されるようになった。
7反だった田はついに1町5反にもなり、小学生になった弟
たちも手伝ってくれるようになった。
後年、姉ちゃんは働いている姿しか思い出せない、と弟に
言われた。
稲刈りを終えた秋~春、村の娘は都会へ女中奉公に行った。
自分も行きたかったが、“裁縫を習わせてやるから奉公は駄
目”と親から言われた。
自分が奉公に行ったら帰ってこないんじゃないか、と親は心
配したらしい。
この方は可愛いお顔のお年寄りだ。
加えて働き者であれば若き日都会で見込まれたうえ、長い
奉公や嫁入り話などを親は恐れたのかもしれない。
さて裁縫は当時の娘さんの大切な修養の一つだ。
小生の同級生のお母さんはかって裁縫の師範で、冬にな
ると近隣の村から大勢の娘さんたちが泊まり込みで習いに
来たという。
場所は違うが、くだんのおばあちゃんもそうして習っている。
話変わって終戦後のこと、高等学校に行かせてもらえず、
中卒で煙突女学校に行ったという方の話を聞いたことがあ
る。
煙突女学校とは紡績工場のことで、なぜ学校かと言えば、
工場の外見が学校に見えなくもない事が一つ。
また工場では仕事のほかお花、裁縫、習字、社会学習など
の時間が設けられ、学校のような側面もあった事に由来して
いるようだった。
振り返れば農作業や奉公、裁縫や煙突学校などの事で、皆
さん最初は遠慮されるが一旦語ればちゃんとした言葉で話を
される。
苦しい時代を生き抜いた体験が奥底のプライドとなって、生
きているように感じられるのである。
較べて一旦事あれば多くの詭弁を弄し、終始うろたえる最高
学府出という某知事などは、本当に滑稽に見える。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日、京都へ修学旅行に行ったという孫から八ッ橋が送られて
きた。
何年か前、ある孫が同じ先の八ッ橋を送ってくれた。
焼いた八つ橋は自分の関西への修学旅行以来の好物だ。

↑齋藤尚明氏の湯呑で茶を飲み、さっそく美味しくいただきました。
R君、旅行は楽しかったことでしょう、本当に有り難うございました。
夏の炭焼き小屋で父と食べたくじら汁。
夏至を迎え夏の盛りとなった。
先日、昭和21年生まれで桑取村横畑(現上越市)
ご出身の女性から炭焼きの話を聞いた。
仕事の合間なので短時間だったが、興味深かった。
遡ること中学時代の村はまだ炭焼きを行っていて、
山中に炭焼き小屋があった。
土曜日午後、学校から帰ると父の小屋に行った。
一人で入る山は怖く、突然大きな鳥が飛び立つ時
など特にびっくりした。
出来た炭を俵に詰めて運ぶのが仕事だった。
一つ30キロもある俵を二つ背負って山を下りた。
炭焼きで忘れられないものにくじら汁がある。
かたまりで買った塩くじらが小屋に置いてあった。
夏になるとユウガオやナスが入り特に美味しかった。
炭火でコトコト煮て父と食べたのが忘れられない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鵜の池の舟着き場。
昨日は、かって上越市は大潟区の鵜の池で、舟を
使って牛馬の飼い葉を刈っていた事を書かせても
らいました。
当時の船着き場とおぼしき場所は見当が付いてい
ましたので、本日午後行ってみました。
長崎集落の東の端で、鵜の池の西側に近い所です。
かねて農業用水の取水を行う水路だろうと漠然と思
っていた場所でした。

水門で休んでいたご近所のお爺さん。
向こうの鵜の池へと水路が開けている。
お爺さんから以下のような話をお聞きしました。
・ここには各家が持っていた田舟が置かれ、賑
やかだった。
・近隣では主に牛を飼っていた。
・池は牛が好きな「カツボ」という草が沢山生え
ていたので主にそれを刈った。
・葦(ヨシ)も生えているが軸が固く、牛は喜ば
なかった。
・自分は夕方に舟を出した。
・刈った草はそのまま牛に与えたが、冬は藁に
米や麦のぬかを混ぜて与えた。
・夏、池が干上がった時にカンジキを履いたが
不
自由なほど足が埋まることは無かった。
兵役で大陸へ行ったというお爺さんは遠くを見
ながら昔話を話してくれました。
つゆの晴れ間、心地良い風が吹いていました。
池のふちからトコトコ電動カーに乗って現れた
老人は患者さんでした。
土曜日午後は良いひと時でした。
※草にぬかを混ぜて動物に与えたと記載しまし
たが、それは冬期間にワラを与える場合のこと
でしたので訂正させていただきました。
昔は鵜の池に舟を出し、飼い葉(牛馬の餌)を刈ったらしい。
上越市大潟区の二人の方から、その昔鵜の池に舟を
出して飼い葉を刈ったとお聞きした。
今春以来皆様に昔の田植えの話を聞いてきたが、およ
そ農家は農耕用に牛馬を飼っていた。
牛も馬も毎日餌として大量の草を必要とする。
草刈りの時間は早朝か夕方、中には朝暗いうちから遠
くへ出かけたという人もいた(しかも少なからず子供が
関わっていたらしい)。
場所は田のアゼや土手や道ばた、あるいは共同ないし
私有の草刈り場だった。
そんな中でAさんBさんから、「鵜の池」に舟を出して草
を刈ったと聞いて驚いた。
舟は底が平らな田舟、池は浅いので棹さして進み、舟一
杯刈ったという。
本日年配のBさんによると、夏はしばしば池が干上がり、
目的地まで行けなくなったらしい。
そんな時は途中まで舟で行き、カンジキに履き替え干上
がった池の底を歩いた、という事だった。

↑県道78号線を挟んで上方(東より)が朝日池、左下方
が鵜の池。(Googleマップをキャプチャーしてマーク)
Aさんの集落は朝日池に近いがそこに草はあまり無い。
そこで県道を越えBさんの近くの鵜の池まで出かけた、
という。

↑本日の朝日池。向こうにAさんの集落がある。
周辺に飼い葉向きの草は少なく、池面にヒツジグサが多い。

↑本日の鵜の池。周囲や浮島部分は多くの草に覆われ、
なるほどここで刈ったのか、という景観が残る。
草で言うと二つの池は大きく異なる。由来が人工的か自
然的かの相違かもしれない。
朝日池や鵜の池には中学時代までよく釣に行ったが、
かって舟で草刈りが行われていたとは思ってもみなかっ
た。
池が干上がるほどの炎天下の池底を歩き、鎌を振るい
背丈ほどの草を刈る。
それを背負って何度も舟まで通い、岸へ運び、そこから
荷車かリアカーに積んで家まで帰ったのだろう。
毎年、毎夏、、、何という苦労だろう。
いつしか皆で同じことをしていた時代からテレビの時代に
なり、同時的に農業の機械化も始まる。
若者はどっと都会へ出た。
比較的若かった長男のAさんは、農業がばかばかしくなり、
勤め人に転身したという。
機械化に対応して圃場や水管理など全体が製造業と平
行して様変わりして行ったのはそれとなく目にした。
結果、多くの農家は機械化された大農式の営農家に仕
事を委託するようになって今日に至っている。
ところがそれ以前のことを全く目にしていないのも不思
議なくらいだ。
以前ブログで田植えの事を書かせて頂いたように、見よ
うと思えば舟による草刈りも見る事が出来たはずである。
その事で言えば、物事は見たいと気づいた時(自分にそ
の価値が何とか分かるようになった時)、しばしばそれは
すでに終わっている。
遅きに失したが、この年になって少しばかり関心分野が
広がり、喜んでいる。
それにしても日頃何かと頭の良い人ばかりに目が行き、
どうすれば生きるにふさわしいか、いつまでも現実は悩
ましい。
今にして思えばということ。
良い季節となり近隣の田も田植えは終了しつつある。
さてまた田植えの話で申し分けありません。
「今は10条植えなんていう凄い田植機があり、5反くら
いは何回か往復するだけで終わらせちゃう。兼業や手
伝いの家族の都合なんかで、田植えは週末にちゃっち
ゃっと済ますんです。人も二人か三人で、昔とは大違
いです」
話はその昔、そうとめ(早乙女)をした若いおばあちゃん
の感想だ。
今でも田植えは見た目と違い楽ではないと思われる。
また最盛期の田んぼは田植機が動き回り、人も出て、
私は好きだ。

↑お年寄りも腰掛けて応援団として田植えに参加しているようだった。
早乙女だった日の熱い血がよみがえるのではないだろうか。
その昔、見渡せばあちこちで十人、二十人の人、それ
もある時代、ちゃんと着付けた早乙女達はじめ、大勢の
男衆がいで立った田植えは、どんなに壮観な眺めだっ
たことだろう。
但し苗の仕度、人集め、複雑な段取り、雨降り、、、。
田植えは持ち主にとって目出度い一方、重い責任とスト
レスの行事だったに違いない。
自分なども見ようと思えば過去いくらでも大勢の田植え
を見ることが出来たはずだが、当時は見る目がなかっ
たとしか言いようがない。
親の話なども同じで、居なくなってから聞いておけば良
かった、と思うことばかりだ。
一方、子は要領を得ず、親も馬鹿にしてまともに相手に
してくれない、ということもあり、難しいところだ。
昔の田植えの続き。
過日お二人のお年寄りから早乙女として田植えをした話
を記載した。
手植えによる盛大な田植えは当地で歩行型田植機
が普及する昭和50年代後半~60年前半あたりま
で続いたいたようだった。
※但し後に兼業農家が圧倒的となり、自家用車が普
及し田植えは次第に地味になっていったという。
機械化では稲刈り機に較べ田植え機の機能と構造は
は複雑で、現在のように大がかりな実用が可能になっ
たのは最近らしい。
先日記載の後、さらに何人もの方から昔の田植えの話
をお聞きして早乙女の追加や新たなことがらなど掲載し
ました。
先日の疑問や追加など。
●田植えのため早乙女たちが往き来する事の呼び方?
「ユイ(結い)」や「ユイッコ」と呼んだ。
(※前回早乙女を「しょうとめ?」と書きましたが、「そうとめ」
かもしれません)
●田植えに行った場合、行った先の娘さんたちも一緒に
植えたのか?
一緒に植えて、多いときには10人を越えることがあった。
●娘さん達は苗を植えたが男は何をしたのか?
苗床から苗取り、苗運び、苗結び、格子や定規で田の目
安を付けるなどを行った。
●男の子たちは何をしたのか?
植える人のために、田んぼに束ねた苗を投げたり、格
子持ちも若い男の仕事。昼食や水も運んだ。
【新たにお聞きしたことなど】
●多いときには一週間から10日で4,5カ所を回り、と
ても疲れた。
上着、腰巻き、タスキ、手甲やきゃはんは自分で縫った。
但し半幅の帯だけは買った。
田植えばかりでなく「植え直し」という作業があり大変だ
った(初期の田植機の頃かと思われます)。
(昭和13年生まれ 吉川区川崎のご出身)
●子供の時から田仕事を見ていたので、初めての田植
えも平気だった。子供時代の田仕事は半分遊びみたい
な感じだった。
(大正12年生まれ 吉川区梶のご出身)
●田植えの前の日、食べ物を包む朴の葉を取り行くが、
木が高いので男の子が登って葉を落とし、女の子は下で
拾い集めた。
近郷近在、老若男女が大勢入り交じって話の花が咲き、
田植えは一年で一番大騒ぎの楽しい行事だった。
(大正6年生まれ 名立区桑取西横山のご出身)
●結いの往き来は当初バスだったが、後にタクシーで迎
えが来るようになった。
早乙女に出る人が少なくなったためだと思う。
(昭和11年生まれ 大潟区内雁子の男性)
●服装はハンチャと言うカスリの上っ張りを着る。
袖の先の内側に白布をつけそれを折り返して表に出
した。
黄色の帯は当初メリアスで縫ったが後に買うよう
になった。
昼食の煮しめが特に美味しかった。
朝早くから夕方遅くまで植えたが遅くなると余計にお
金を貰った。
自分は一人っ子で我が儘に育ったが、誘われて初め
て結いに行き、みなと同じ仕事が出来て嬉しかった。
近隣の田植えにはチャリンコで行った。
(昭和13年生まれ ご実家吉川区西の島)
●家が地主だったため田植えをした事がなかった。
戦後、貯金を封鎖され、広い田と山の巨木を取られ
た。
ある日突然田植えをさせられ、さんざんな目に遭った。
みな上手にドンドン先へ行くのに、自分は田の中に
取り残されて動けなくなった。
その年、吉川区の泉谷や竹直へも行ったが、もう無
理だと思い、看護婦の勉強をすることにした。
(昭和8年生まれ 大潟区農村部の女性)
田植えに限らずお年寄りの若き日の話は夢まぼろし、
あるいは物語のようです。
いま10代、20代の人も5、60年経ったら懐かしい
昔話を生き生きと語って貰いたいと願うのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日診療所の上越市大潟区はひどい暑さにみまわれた。
33、4度の気温はこの日全国1位となった模様。
一転して明日はぐっと冷え、場合によって半分程度まで
気温は下がりそうだ。
若き日、お年寄りたちは早乙女として隣町の田植えに行った。
先日昭和10年生まれの方から、娘時代の何年か毎年、
隣町の農家に行き田植えをした話をお聞きした。
数日後昭和4年生まれの方が、同じ話をされたので、少々
驚いた。
お二人とも頸城区の農家から大潟区へ嫁がれている。
お話はいずれも実家に於ける娘時代の体験だった。
田植えをする娘さんたちは「しょうとめ?そーとめ?(早
乙女)」と呼ばれたらしい。
当時の年令と住所は異なっているが早乙女として田植え
に行った先は偶々いずれも現在の柿崎区の上直海(かみ
のうみ)だった。
お聞きした内容はおよそ以下のようなものだった。
15才~20才ころ田植えの時期が近づくと親は新しいカス
リの生地を買ってきて、娘達は自分で野良着を縫った。
田植えは近所の娘さん達5,6人とバスに乗って行った。
新井柿崎線を長峰で降り、そこから上直海まで数キロ歩
いた。
田植えの身支度はピンクの腰巻きをしっかり付け、上から
新しい野良着を着て黄色の帯を締めた。
手甲、きゃはんをつけ、赤いタスキを掛け、手ぬぐいで顔を
覆いすげ笠を被ると身が引き締まり、晴れがましい気持ち
になった。
雨降りでは持参した箕をまとった。
男衆は苗の仕度をし、格子を置いて植える目安を付け、
植えるのはもっぱら早乙女の仕事だった。
午前午後の途中に休みがあり、お茶とともにボタ餅やキナ
コ餅などの甘くて美味しい食べ物が出された。
それらは大きな朴の葉にくるんで用意された。
お昼は足を洗って上がり、昼寝をしてから午後また植えた。
一日が終わった夕食に赤飯とともに、刺身や煮物に焼き魚
など贅沢なご馳走が振る舞われた。
行った農家で2晩ほど泊まったが、若かったせいか辛かっ
たり、腰が痛くなるなどの記憶はない。
こちらの田植えの時に、今度は行った先から娘さん達が来た。
彼女らを迎える前に、朴葉を取りに行くのは自分たちの仕事
だった。
(地元の娘さんと遠来の娘さんと一緒に田植えをするのかは
お聞きしていませんでした.。
両地を結ぶ親戚筋が早乙女の往来を「いっこう?」として取り
まとめているようでしたが、これも詳しくお聞きしていません)。
男衆が段取りをつけ娘さんたちがが本番の苗を植える。
お話から田植えは通常の農作業と異なり、豊作を願うハレ
の神事でもあり、産む能力を有した早乙女たちは田の神の
使者の役をも委ねられているように思われた。
お二人とも思い出しながら気持ちが昂揚されるのか、生き
生きと話してくださった。
昨今の社会は一見自由で便利だが何かに付け複雑で、自
身の立場や役割を明瞭に把握するのにしばし困難を伴う。
そのうえ人生は長く、存在理由の曖昧さはさらに広がろうと
している。
較べて昔の人の人生は短い。
それで農村などでは年令などに応じて立場、役割が適宜一
般化され諸般無駄の無いよう計られていた風に見えた。
白い馬の家(うち)。
先日の在宅訪問である高齢のおばあさんを訪ねた。
90才なかばを過ぎたおばあさんの反応はぱっとしなかったが、
子供の頃の田んぼの手伝いの話になるとどんな質問にも細か
に反応された。
古いことほど明瞭になることもあるが、そもそも田畑の仕事は人
を無心にさせる作用がある。
付随して思い出したくないことがあっても、それだけは回想でき
るのかもしれない。
おばあさんと話していると今度はお嫁さんが加わって、以下の
ことをお聞きした。
“実家のおばあさんの話では、昔、家に白馬の農耕馬がいた。
娘時代おあさんが特に面倒をみたのでなついて、よく馬に跨が
って走ったと聞いた。
白い馬は珍しく、実家は「白い馬の家(うち)」と呼ばれていたよ
うだ”
世の中には思わぬ話がある。
白馬と言っても葦毛であろうが、やはり農耕馬では珍しいことだ
ろう。
集落を駆け抜ける白馬と若き日のおばあちゃん。
春秋の水田でも目立っていたにちがいない。
「白い馬の家」
ドラマのイメージが重なる。
外国人も“どっこいしょ”と言うのだろうか。
午後休診の木曜日、好天に恵まれ庭に土と肥
料をくべた。
「み」に園芸用の土を採り、トンプンを混ぜて撒
いたり地面に混ぜたりする。
結構重いので持つときに「どっこいしょ」とよく
言った。
老人向きの言葉だが、もともと非力な自分はか
なり以前から言っていたような気がする。
仕事場でお会いするお年寄りたちは本当にどっ
こいしょと皆さん言う。
座る時も立つ時も言っては、ご本人は笑っている。
「どっこいしょ、って言うと立てるんです」とも仰る。
ところで外国でどっこいしょ、のニュアンスの言葉
はあるのだろうか、とふと思った。
周囲に外国人はいないし、映画やテレビの場面
でもすぐには思い浮かびにくい。
少々検索してみたが、文面だけではぴったりという
感じにはならなかった。
英語は「ウッ」などのうなり声は普通のようであり、
「here we go」は「せーの!」のようであるし、
「upsy-daisy(アップシーデイジー)」は主に「さあ、
さあ」や「頑張れ!」などと人に言う言葉であろう。
oops!(ウープス!)は「おっと!」に似ているが、
どっこいしょもあるのだろうか。
フランスでは「ウッ プラー」、イタリア「オッ プラー」
があるようだった。
「せーの」かもしれないが、語感から「どっこいしょ」
のイメージがしないでもない。
無いと記載された国も多かった。
しかしうなり声やつぶやき、あるいはおまじない
めいた「どっこいしょ」は、
どの国にもあるのではないか、と期待している。
同じ人間で日本人だけが「どっこいしょ」的な声を出
すとは少々信じがたいが、どうなのだろう。
おばあちゃんってすごいなー 亡くなった人を思い出す。
昨日の空は澄み渡り素晴らしかった。
その空のことであるおばあちゃんと初孫が交わした話が
ある。
その昔おじいさんがまだ元気で孫が3,4才だった頃の
こと。
おじいさんは四六時中孫を三輪車に乗せて可愛がった。
おばあちゃんとも仲良しでよく話をしたという。
ある日以下のような会話があったらしい。
「おれはおまんのこと、死んだ後もずーと見ていてやるからね」
「どうやって見るの」
「空の上から見るんだわね」
「おばあちゃんてすごいなー空へ行けるの、どうやって行くの」
今ではその孫もすっかり生意気になりました、ということです。
確かに子供には天使のような時代がありますね。
さて心の問題ですが、亡くなった人が一番喜ぶのはその人を思い
出す時だ、と聞いたことがあります。
なるほど、です。
親の事では楽しい事つらい事ともにあります。
楽しい事や楽しい人を思い出すのは比較的容易ですが、
つらい事(人)を思い出すのは普通気が進みません。
でも時にはそれを越えて思い出す事は良いことではないか、
ということなのです。
広げて、どんな人のことでも、亡くなった人を思えば、その人は
慰められたり喜んだりしている、ということも。
忙しいとそうそう出来ませんが、時には短時間でも良いらしいの
です。
何かわかるような感じがします。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 聴老(お年寄り&昔の話)
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 良いご一家の話。
- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。
- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。
- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。
- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。
- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。
- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。
- 自然の末席で。
- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。
- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。
- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。
- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。
- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。
- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報
- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。
- 25年初日 A君の書と芸術。
- 明日から2025年度の開館。
- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。
- 今冬の冬鳥見おさめ。
- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月