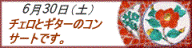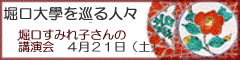聴老(お年寄り&昔の話)
引きこもりの一日 秋野菜の新鮮。
本日勤労感謝の祝日、残念なことに一歩も外へ出なかった。風邪でも引かない限りこんな日はまずない。
身体障害や施設入所の申請書類、介護保険意見書、会社の健診サマリー等々作成しなければならない書類は引きも切らない。
新潟市の月刊茶道雑誌「石州」への寄稿「樹下美術館だより」は一年にして頂き、12月号で終了となった。幾分身軽になったが、予定通りであれば文芸たかだ来年1,3,5月号の表紙を依頼されている。描いては直していた1月号を本日なんとか仕上げた。
たまたま台所にあった白菜の新鮮さに目を奪われる。ある方が作ったもので、引きこもりの日にあって心洗われた。一緒の大根も輝くばかりだったということ、妻は感心しきりだった。
野菜を作られた方は、かつて歯を食いしばって舅・姑さんの介護と看取りをされました。介護や看取りは人生の一大事業に匹敵しましょう。それぞれの立場立場で完遂された方々には、他に得がたい芯のような徳が背中を通っているのを感じます。
いま野菜作りに勤しむ人。頂いたものの清々しさから、磨かれた心が伝わるようでした。
本日は外出の代わりに、スクワットとバランスを組み合わせた自分流の体操を繰り返した。
箱根の人 小学時代にキャディさん。
87才のAおばあさんはいつもにこにこしている。お家から当院までは、幾つかゆるい坂のある2キロの道のりだ。先日、どうやって来られましたか、とお尋ねした。
「三輪自転車をこいで来ましたよ」
自転車とはお年を考えれば驚くべき脚力だ。実はAさんは私が知っている当地で唯一の箱根出身者である。
「山で鍛えた脚なんですね」
「はい、小学校でキャディもやりましたから」
「えっ」
自転車のあとはキャディさん、二度びっくりだった。
「仙石原、仙石原のゴルフ場ですよ。私は小柄だったのでみんなより一年遅れましたけどね」
ああ、嘗て神戸だったか黎明期のゴルフ場の写真で、着物を着た子どものキャディ姿を見たことがある。Aさんはそれを箱根で経験されたんだ、なんて貴重な人だろう。
子守、奉公、昔の田舎の子どもたちは早くから家を助け、社会と交わった。なるほど箱根にキャディさんか、しかも人気だったらしい。
 Aさんがキャディをした日本で最も古いコースの一つ富士屋ホテル仙石ゴルフコース。大正6年、開場当時の写真。確かにキャディさんは子どもたちだ。
Aさんがキャディをした日本で最も古いコースの一つ富士屋ホテル仙石ゴルフコース。大正6年、開場当時の写真。確かにキャディさんは子どもたちだ。
(富士屋ホテル、仙石ゴルフコース開場95周年ホームページより©)
写真は研修だろうか、大人に混じる子どもたちは愛らしく、真剣だ。仙石原でキャディを経験し、後に自らゴルフを楽しんだ人達は少なくなかったという。
ところでその昔、私は家族と箱根で正月を過ごしたことがある。雪国と違い連日の好天で日差しは眩しいほどだった。
後年越後へ嫁いだAさん、雪と田仕事の辛さは想像以上だったらしい。
「一生懸命やりましたよ」
Aさんがいつもにこにこされるのは、かつて浴びた箱根の日差しのせいですか。
間もなく駅伝が始まりますね。
残暑の根知 超高齢者の共通点
大陸へ向かう台風の影響で熱風に見舞われた敬老の日。私用で糸魚川市へ出かけ、帰路は根知まで足を伸ばし、慈雲山・金藏院のひなびた石仏と堂々の駒ヶ岳を見て帰って来た。
さて敬老の日ということで若干を記してみたい。
筆者が拝診している年長者で、100才を越えている女性が三人、間もなく100才を迎える男性が二人いらっしゃる。
女性の最高齢者は103才になられた。一昨年、大腿骨骨折の手術をされ、見守られて歩行器で移動される。単純ながらちゃんと会話が可能で、愚痴や恨み言をあまり口にされない。
100を越えられた女性達の身体や性格に関する明らかな共通点は見い出しにくい。但し若い頃から働き者で、自立を心がけ黙々と生きてこられた経緯がうかがえる。
これに対して最高齢の男性お二人は驚くほど似ている。記憶や記録、整理整頓に優れ、責任感が強く、世話役として長く活躍されるなど、几帳面さにおいて見事に一致している。
ある種不思議な(当然でもあろうが)ことだが、これら超高齢者は男女とも必ずしも十全の健康体といえない点も同じだ。心臓、脳血管、腎臓機能などにそれぞれ問題を抱え、あるいは骨折歴を有しながら、留意を重ねてこられている。
騒ぎとなるような認知症状がみられないことも目を惹く。
ご本人たちの日々淡々とした心がけのほか、ご家族の温かな観点も一緒だ。
さまざまなな契機で。
80半ばを過ぎたAさんは、浜や松林の清掃ボランティア、大がかりな日曜大工など何でもなさった方だ。ところがこの一両年頭が重い、胸が苦しい、やる気が出ない、と嘆きが先立つようになった。
いくつか病院を受診されたが、脳動脈硬化と老人性うつと言われるだけ、と険しい顔で不満を口にされる。家では何かと奥さんに辛く当たるようにもなった。
デイサービスへ行って生活リズムを変えてみることを何度か提案した。しかし、まだそんな所へ行く年ではない、の一点張り、活発だったAさんなら仕方ないのか。
試みに精神安定剤を変え、さらにここを受診してみましょう、とある病院を紹介した。
数日後の夜間、今度は奥さんが片方の眼を中心に三叉神経痛に似た痛みの症状を訴えられた。往診先で神経内科を受診することに決めると、傍らのAさんを見ておや、と思った。
いつもの険しい顔が和んでいる。聞けば、本日受診した病院は女医さんで、とても親切だったと仰る。優しい女医さんが効いたのか、変えた薬が効いてきたのか、以前のAさんらしい温和な表情が蘇っていた。
さて、奥さんは4,5日の入院の後、無事帰宅された。奥さんの入院中、何処へ行った、何の病気かと、Aさんは大変心配されたらしい。
奥さんの退院後、ご夫婦は以下の様な話をされたという。
「今度私はデイサービスに行ってみようと思うの。お父さんもどう、一緒にに行ってみようさ」
「おまんが行くならオレも行ってみるか」
思ってもみなかった相手の入院、それに女医さん?薬?老後であっても、いや老後ならばこそ、人や関係はさまざまな契機で変ることがある。
このたびは良い方向が期待される。やはり諦めることなかれなのだ。
幸福な親子 今日の夕焼け。
超高齢者(およそ85才以上の方)にとって、夏は冬よりも危険ではないだろうか。ご本人がさほど辛さを感じないうちに高熱を発したり、意識障害に陥ることも希ではない。熱中あるいは脱水症であり、時として尿路などの感染症を併発する。
90半ばのおばあさんはまる一日意識が無かった。しかし数日の点滴のあと、少しの粥、それに味噌汁とお茶で回復に向かっている。ひごろ息子さんは母親の車椅子を押して散歩に出るなど熱心な介護をされる。
不十分な食事を補おうと栄養リキッドをお出しした。それはとろりとして甘い。プリンがダメだったので心配したが、「甘いのう」と仰って飲まれたという。一安心だ。
「これはおまんの乳だから甘いんだわね」とせがれさん。
「あー、どおりで旨まかった」と患者さんは喜んだらしい。
おばあさんには一定の認知症がある。しかしこんな素晴らしい会話を交わされる親子もざらには居まい。我が子のようなもんですから、と彼はよく言う。私も晩年の母を好きになったが、せがれさんの足許にも及ばない。
さて今日の四ツ屋浜の夕焼けも変化に富んで素晴らしかった。夕焼け度8は十分にあったのでは。
19:18
夕刻にかけて高いむら雲やすじ雲が広がる日は、綺麗な空になることが多い。華やかなものは日没後から始まる。
TVならきっと音楽が入ることだろう。しかし実際は当然音も無く展開する。およそ15分、壮大なのに静かであることで余計神秘的だ。
これから本番。鵜の浜温泉やキャンプ場のお客さんにも、ぜひ忘れられない夕焼けに出遭ってほしい。
安否確認は双方向。
多くの人が連休中に動いた。東京にいる知人も盆暮れのほかしばしば実家に帰ってこられる。連休にお話を聞いた。
郷里の実家で独居する老親を訪ねるのは、「親の顔を見ることと、自分の顔を見せること」の二つ意味がある、と仰った。確かにである。
訪ねなくとも普段から電話で安否を確認されている方もおおぜいいらっしゃる。実家のご近所さんやヘルパーさんとの連絡も有益だが、ご本人のお声が一番だ。その時、電話の向こうでお年寄りも子と家族の無事を案じている。
お年寄りは私たちが考える以上に敏感なようだ。どんなに年取っても多くの安否確認は確かに双方向であろう。
軍隊の泉。
2月に脳梗塞で長い在宅療養の男性Sさんが激しい痙攣を起こした。90才になった人で、以前は感染症による高熱で何度か発作を起こした。このたびは過剰な暖房で部屋は暑く、汗を掻いていて冬の脱水だった。
入院をせず点滴で快復され、今では鈍かった反応は戻っている。今日伺うとぼんやりされていたが、私が敬礼をすると蒲団から手を出して敬礼された。その後は満面の笑みだった。戦前のSさんは何度が中国へ出兵されていた。
「角度は30度です。海軍は15度」、入れ歯を取った口をモグモグされなが手の角度を仰っている。以前からすっきりしたお顔と体型で素直な気質の人だ。
何度か軍隊時代のことを聞いていたが、以下の話が印象に残っている。
●新潟県のN日赤の病院長だった軍医が居て、先生のお父さん(私の父)のことを知っている、と言われびっくりした。遠い外地で知らない上官から、自分が知っている人を知っている、と言われると嬉しかった。
●上級将校は柳行李(ヤナギゴウリ)というものを持って移動した。ある日、その将校が私に「緑の地平線を歌ってくれ」と言った。私はその唄を知っていたので歌おうと思った。すると将校はヤナギゴオリからバイオリンを取り出して前奏しはじめた。私は大声で歌ったが、とても感動した。
柳行李に何が入っているかいつも考えていたが、まさかバイオリンが出てくるとは思わなかった。
●T大尉は上越出身の軍医だった。戦争が終わると「英語を教えてやろう」といって虹やポストや道など、見えるものの単語を習った。とても良い発音だと思った。
軍隊にも泉のような人、泉のような時間があったらしい。
70才、折々の後ろ向き 雪は一休みか
70才になり一日がより貴重に思われるようになった。本日は運転免許の更新申請に行った。受付で写真を撮り、簡単な書類に記入するだけで実にあっさり終了した。
「講習など何もないのですか」と尋ねると「高齢者講習をしっかりやっていただきましたから」と言われた。確かに何ヶ月か前に実技も行ってしっかり済ませた。
ところで70才は聞いていたようにあらためて重い。何かぬかるみや風圧に似た抵抗感を覚える。
昨年12月に初めてドッグを受けて多少ショックを受けた。かくなる上はさらに食事に気を付け体操を心がけたい。身辺などを単純にして身軽になろう。できればぬかるみは子どものように楽しみ、風が吹けば力を抜いて背を向け、来た道などを眺めながら進んでみよう。
折々後ろ向きになるのはいい考えだ。必要な前の様子は、過ぎていく後ろを見れば大体分かる。自然とそんな風になってきたような気もする。
 午後から晴れた仕事場界隈。
午後から晴れた仕事場界隈。
内陸・山間は豪雪なのに、幸い大潟区は平年並みかという程度で推移している。
予断は許されないが雪は一休みと予報された。
神田の製図学校とは? 災害的な豪雪
さて昨日書かせていただいた花札を制作された方が仰った製図学校(図面学校→製図学校)については全く知りませんでした。インターネットを調べてみると中央工学校という学校が出ていました。
場所が神田だったこと、女子製図科が設置されていたことから、同校ではないかと思いました。
ちなみに以下学校の沿革の一部です。
●1909年(明治42年): 即戦力工業技術者育成を目的として、東京市神田区一ツ橋通町20番地に「中央工学校」を創立。建築・機械・電工の3学科を設置。
●1918年(大正7年): 女子工業技術者育成を目的に女子製図科を設置。実践的な技術者を輩出して教育界・産業界から注目と期待を集める。
※田中角栄は1936年(昭和11年)、同校土木科の卒業生のようです。。
早くから女性に開かれた技術教育。そこへ飛び込んで行った人が当地にもおられたとすると何か元気づけられます。次回の訪問でまた続きをお聞きしてみたいと思います。
さて当地上越市大潟区の昨晩の積雪は、庭で46㎝でした。本日は小雪が降ったり止んだりしましたが、積雪の高さは昨日とほとんど変わりなく見えます。
ニュースが伝える内陸の豪雪はすでに深刻な災害レベルです。昨年から見られる季節進行の遅れを考えると、心配です。
週末の雪は一休みしてくれますように。インフルエンザが流行してきました。
手作りの花札 製図学校 お前も運転してみろ
下の写真は、過日紹介させていただいた患者さんの手作り花札です。作ったのは80才代後半のお年寄り(おばあさん)でした(いつ頃使ったのかはまだ聞いていません)。
活発な方でしたので、昨年夏、圧迫骨折の痛みで寝たきりになりかかた際のショックと悲観は、見ていられないほどでした。訪問診療によって骨粗鬆症の注射を続け、幸い今ではなんとか居間へと歩かれるようになりました。
そんな折りに見せていただいたのがご本人手作りの花札です。絵や厚さなどの形態があまりに良くできていて驚くと同時に、如何に作ったかに大変興味がありました。
一ヶ月前の訪問ではケント紙にピースの中箱の紙を貼り、絵は自分で描いたとお聞きしていました。しかしそれにしてもである。
本日訪問すると傍らに製図道具と材料が置かれていました。コンパス、からす口、雲形定規、そして切り紙などです。これは一般におばあさんが持つ物とは違います。
お聞きしたのは花札の作り方の続きでした。今回は紙は一般のケント紙三枚では厚すぎるので、二枚を貼りその上にピースの中箱の紙を貼るとほど良い堅さになる。曲線は出来るだけ雲形定規を用いた。線はペンとからす口で引いたなどと伺いました。
道具も方法も素人の域には思われませんでした。どうしてこんなことが出来るのですか、とお聞きした所、以下のようなお話をされました。
自分の父はこの土地の自動車屋だった。私が高等小学校を出ると父は自分を東京の製図学校へ進学させた。高等女学校は時間の無駄、花嫁学校みたいなものだからという理由だった。
神田の図面学校で教えてもらった方法で、後年子どものためにこんな花札も作った。父は比較的若く亡くなったが、学校時代に自動車に乗せてもらったことがある。その時父はいきなり私に、お前も運転してみろと言い出し、びっくりしたことあった。父は進んだ人だった。
以上がお話の概要です。私自身、からす口も実際使ったことがありません。もっと詳しくお聞きしたいが時間がありませんでした。しかし製図学校といい何もかも驚きです。もしかしたら花札のことでは、お父様のことをお話したかったのかな、とも思いました。
普段お互いに黙っていればただすれ違うだけ。しかし話をお聞きした場合、驚くようなことを耳にすることがあります。かって傍らで聞いているお嫁さんが「知らなかった」と仰ることもありました。
お年寄りは繰り返し同じ話されることが多い。しかし最も大事な事は胸にしまっているのかもしれません。私たちと同じように。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 聴老(お年寄り&昔の話)
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。
- 上越市八千浦中学校の皆さま。
- 小3の凄まじい体罰 その3 終章。
- 小3の凄まじい体罰 その2。
- 小3の凄まじい体罰 その1。
- 小学校に上がるまでジャンケンを知らなかったAちゃん。
- 台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る その2。
- 今朝方の雷雨 その昔、台風後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る。
- 厳しい残暑のなか頸城野の稲刈り。
- ほくほく線のポストカードで。
- 気に入って頂いたほくほく線電車の写真。
- 今年初めての赤倉CC 仕事上の最年長になっている。
- 今年前半の「お声」から 刈り入れ前の田んぼの雀。
- 週末の上京 小5の築地と叔母の周辺そして「横浜事件」。
- 昭和100年、太平洋戦争80年の声無き声を思って。
- お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。
- 来たる10月25日(土)は小島正芳先生の講演会「佐渡島の金山と良寛の母の愛」。
- お盆休みに入って。
- お礼のランチ会。
- 明日夕方は満月。
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月