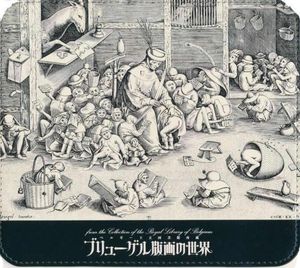食・飲・茶・器
サントリーの限定ワインCENTURYのサプライズ
本日昼、岩の原葡萄園社長・坂田敏さんが貴重なワインを携えて訪ねて下さった。サントリーが営む「登美の丘」におけるぶどうづくり100周年の記念醸造ワインで、1200本の限定「CENTURY」。サントリーからの贈り物だった。何ページもの資料が付いていて、ほんの先だって12月1日発売とあった。
シャトー ラフィット ロートシルトで知られるドメーヌ バロン ド ロートシルト社との提携25周年の祝いも込められ、両社共同で開発醸造されている。
ぶどうは、日本で摘んだカベルネ・ソービニオン、プチ・ヴェルド、メルロを主力に川上善兵衛が確立したマスカットベリーAも入る。 「伝統的なボルドースタイルでありながら、日本をイメージするエレガントなワイン」を目指したと謳われていて、非常に楽しみだ。
それにしてもサントリーホールディングス社から樹下美術館はいつも心に掛けて頂いて感謝に堪えない。2007年の開館に際して副社長・鳥井信吾氏からシャトー・ラグランジュの珍しい白を二本お届けいただいた。また今年7月の岩の原葡萄園120周年では氏みずから来館され1200mlの記念マグナムボトルを頂戴した。このたびは小生の県知事表彰の祝いということ、思ってもみなかった。深く痛み入り言葉もない。有り難うございました。

夕食は岩の原スパークリングワイン「ブラン・ド・ブラン ローズ・シオター」で
牡蛎など
頂いたワインはみな取ってある。齋藤三郎のいにしえの縁とはいえ、ささやかな当施設を気に掛けて下さるサントリーさんには心から勇気づけられる。樹下美術館もさらに先へ向かって成熟を果たして行きたい。
サプライズと、良いお天気に恵まれた1日だった。
越後上越 米山山中(よねやまさんちゅう)の水野
知人夫婦8人で6,7年振りの上越市柿崎区水野に集まった。囲炉裏を囲んであっという間の2時間半だった。いわなに噛みつき、熱いのっぺを頂き、心ゆくまで新そばを楽しんだ。
 囲炉裏のいわな |
 そばがき |
 いわなの卵(こ) |
 新そば |
 古時計 |
 つるし柿? |
銚子屋さんのお父さんご夫婦、若夫婦も優しかった。米山薬師の旧宿場、水野の一夜を心に沈ませて帰ってきた。越後に鄙(ひな)あり、山水に田も海もある。
正午のお茶事
本日、日頃お世話になっている茶道の先生宅で正午のお茶事があった。お炭点前と懐石の初座、濃茶と薄茶の後座、心温まるもてなしを受けた。
小生以外の4人のお客様はいずれもお師範で少々緊張した。しかしご亭主お心入れの印象的なお道具と端然たるお手前に、穏やかなお正客様のリードが相俟って忘れがたい一座建立がなった。このような出会いはめったにあろうはずがない。いつかまたと思いながら一期一会をかみしめた。
ブリューゲル版画の世界展で新潟市へ、そして少々の探索と食事
日曜午後、在宅の患者さんに小康がみられて、急遽新潟へブリューゲルの展覧会を見に行こうということになった。過日、同展を監修された森洋子氏から解説を聴講していたので楽しみだった。
会場の新潟市美術館は人気で、しかも若い人達で賑わっていた。膨大で濃密な内容から、主要なテーマの一つである人間の愚かさと罪が教義や時代を超えることを自然に知らされる。
A3ほどのサイズに数百人の人物と妖怪などの詳細さ。奇想天外な象徴性。風景や船のスケール感と立体感。写真以前の時代にあって凄まじい迫力だ。若者達に混じってこのような絵画を目の当たりに出来たことを幸運に思った。
ブリューゲルの後、同美術館の常設展示も見た。ここにあるとは知っていたが、4点のウジェーヌ・カリエールに出会えて大きな収穫だった。カリエールは樹下美術館の常設展示作家、倉石隆氏が傾倒した作家の一人だ。霧のカリエールと称させる所以がよく分かる。30点近く収蔵されているようだがもっと見てみたい。
樹下美術館も一点カリエールを所有している。ネリーを描いた作品だが、本物であるかやや心配になった。カリエールは市美術館の常設展示室を入ってすぐに出会える。
ところで同美術館は昨年カビや虫の汚染騒ぎに見舞われて、大規模な処置が施された。本日かすかな燻蒸の匂いが残る館内に安心と清潔感を覚えた。
せっかくの新潟の日暮れ、美術館を出て信濃川の河口を見たい一心で車を西へ北へと走らせた。初めて見た窪田町のY字路の風情は大変印象的。
行き着いた河口付近は港湾管理が強力で行き止まりとなる。入船(いりふね)みなとタワーなる少々風変わりな施設の7階展望台から夕暮れの河口を見物した。寂しいところで、この時間に女性1人なら怖かろう。
 窪田町のY字路 |
 入船みなとタワーから見た汽船入港 |
 ぽるとカーブドッチ |
 前菜 |
 デザート |
 出港する佐渡汽船 |
暗くなってみなとぴあにある旧第四銀行住吉支店内「ぽるとカーブドッチ」で食事。楽しめる7種のメニューで3800円はとても嬉しい。
帰りの高速道路から見た秋の花火のやや侘びしさ。家に帰るとヘルパーさんに寝かせてもらった母にいつもの寝息が聞こえて、良い休日だった。
夕陽の四ツ屋浜でお弁当
台風は曲がってしまって新潟県は直撃を免れた。一日中、気温は30度に届かず、澄んだ空に雲がさわやかだった。
以前ノートに書いて以来、夕暮れの海で食事することが私たちの課題だった。午後から休診、雲も良く、急遽今夜は海で食べようということになった。
夕刻、家内は母の食事をチャッチャと作り、2人とも少しドキドキしながら近くの四ツ屋浜へ行った。食事はほか弁で、家内は缶ビール、私はノンアルコール缶だった。  雲が少いためダイナミックな夕焼けにはならなかったが、まるまる入り陽が見られた。開けたドアから海かぜが入り波の音が聞える。想像以上にリラックスしながら食べた。580円のお弁当はオカズが沢山でご飯もいっぱい。十分に楽しめた。
雲が少いためダイナミックな夕焼けにはならなかったが、まるまる入り陽が見られた。開けたドアから海かぜが入り波の音が聞える。想像以上にリラックスしながら食べた。580円のお弁当はオカズが沢山でご飯もいっぱい。十分に楽しめた。
海のそばに住んでいるとこんな楽しいことがあるんだ、と家内。暗くなるまで50分間の海辺。お金も掛からず事故にも遭わず、手間も要らず、と喜びつつ車で3分足らずの家に帰ってきた。
午前中、50名様の団体でご来館頂いた北陸三県の浄土宗寺庭婦人会の皆様、ご不自由ございませんでしたか。ご訪問に心より御礼申し上げます。
鈴木秀昭さんの壮大な侘び、大幹堂の御菓子
連日の猛暑、日干しにされていると仰った人がいました。今夜も脱水による入院や、めまいの方の往診が遅くまでありました。夜間にお願いした病院さんの対応に感謝を禁じ得ません。
さて世更けて気まぐれな風が空を鳴らし、古い家がミシッと音を立てました。台風が近づいているようです。

古代を感じさせる御菓子
数日前にある方から滋賀の御菓子を頂いていました。土用の蕗(いわくがありそうです)と金柑(キンカン)の砂糖漬け、そして鮎を模した焼き菓子でした。近江市猪子町「大幹堂」の製です。素朴で古代の風味を伝えるような御菓子でした。
台風を前に気を鎮めようと、鈴木秀昭さんのお茶碗で抹茶を服しました。我が手で世界を現さんとする鈴木さんのお仕事は本当に衝撃的です。器は口縁から見込み、胴、高台内まで一点の隙間なくおびただしい文様が絵付けされています。余白を重んじた従来の抹茶茶碗にはあり得ない形態です。
焼成は、色グループごとに行い、最後は金や銀で焼くのでしょう、何という手間なのでしょう。
当お茶碗には夜とその反対側の昼が描かれていました。黒を効かせた濃密で壮大な器です。鈴木さんの宇宙をたなごころに服する茶に深い静けさが漂いました。氏ならではの侘びにちがいありません。
今度はぜひ茶室でお点前を、と思いました。
鈴木秀昭さん。
1959年東京に生まれる。1986年アメリカ ユタ州立大学社会学部卒業。1991年石川県立九谷焼技術研究修卒業。1993年 アメリカ クランブルック・アカデミー・オブ・アート大学院卒業。以後 カナダ、オランダ、アメリカで研鑽と制作。
現在伊豆で制作。内外で数多くの個展と受賞歴および美術館・団体の収蔵。
見納めでもいいという夕焼け
今日は雨を待って空が気になっていた。夕食中、カーテンを開けると東の空に小さな虹が出ていた。以前、不安定なお天気の夕刻に虹が出て、素晴らしい夕焼けがあった。
「海へ行ってみよう」と妻に声を掛けて食事を中断した。車で着いた近くの四ツ屋浜はまあまあの夕焼けだった。それでも妻は喜んで、今度ここで夕焼けを見ながら食事をしたい、と言った。
日も沈んで、そろそろ帰ろうというころ、佐渡の方がきれい、という声で振り向いた。北側が赤々と染まっている。出て写真を撮り、車に戻ってカメラを片付けていた。
「凄くなってきたわ」、とまた妻。
見れば一面の群雲に鮮やかな陰影が付き、強くオレンジ色に輝やいている。わずか1,2分だろうか、息を飲むような夕焼けが展開された。
「これなら末期(まつご)の眺めでもいい」。
三人の老親の間で何かと多忙を極める妻は、まじまじと夕焼けなど見ることが無かったのだろう。食事を中断して見に来てよかった。
夕焼けならこれからもっと素晴らしい日があろう。そんな日にこの丘で食事をするのはいいかもしれない。私は飲めない口だが、その時は代行を頼もう。
帰って食卓に戻ったが、もう十分だった。
今日は小千谷からもお客さんがお見えになった。私の植物画やシーグラスの絵はがきが一週間で150枚ほど出たと聞いた。
南摩羽峰の屏風に紅茶
降ったり止んだりしながら雨脚が強まっている。気温も下がり、生ける者みな一息つける。ただ降りすぎだけは許してもらいたい。

夏の午後會津藩士の屏風引き 冷えた紅茶を影に浮かばす sousi
南摩綱紀(羽峰)の屏風を居間に置くようにした。二曲一双を開くと藩士の静かな高揚感に包まれる。こうすることも先日朴斎記念館を訪ねたお陰か。それにしても再三のアイスティーで恐縮です、逆光が気に入りました。
板倉、そして増村朴斎記念館

今日の熱い昼、樹下美術館でトーストを食べて所用の妙高市へ行った。用事の後、母が三泊のショートでお世話になっている板倉さくら園を訪ねた。
まあまあの母を明日迎えに来ることにして、気になっている近くの増村朴齋記念館に寄った。しかし施錠がされて入場は叶わなかった。予め電話が必要なようだった。
ところで、増村朴齋は上越市板倉区に私費で有恒学舎(現・有恒高等学校)を設立した民間の偉人だ。朴斎の父・度弘(のりひろ)に影響を与えたのは高田藩で謹慎した会津藩士・南摩綱紀(なんまつなのり、号:羽峰)だという。また若き會津八一が同学舎の英語教師を勤めていることは有名。
もともとあまり詳しくはなかったが、拙宅に南摩羽峰の屏風と會津八一の短冊がある。また八一の揮毫になる巨大な朴齋碑の前で八一本人と齋藤陶齋が並ぶ写真を齋藤尚明氏からお借りしている。そのようなわけで、一度は訪ねてみたかった。
ゼバスティアン
ゼバスティアンはドイツの若者だ。7年前、彼が高校一年生当時、上越市の頸北ロータリークラブにおける交換留学生として責任者S氏宅を軸に一年間のステイをした。
電車で上越高校へ通い、剣道にも励んだ。高校の担当者に恵まれて日本語を良く覚え、地域と家庭に親しんだ。
私の所では一ヶ月半のステイだった。ある日、ドイツの子どもの遊びと言って、隣の雑木林にネズミ取りのカゴを仕掛けた。一週間も空振りだったが、必ず掛かると通した。後日見事に捕った時は大はしゃぎだった。
大好きな囲碁では負けると床を転げ回ってくやしがったが、すぐに私を負かすようになった。
帰国して2年後、家族5人で当地を訪ねてきた。我が家の訪問の際に拙いテネシーワルツを弾くと、皆でダンスをはじめた。仲の良い家族の情景は眩しかった。

成長した彼。樹下美術館裏の農道で。
それからさらに5年、このたび自国の大学院進学前の休暇で三回目の来日を果たした。昨日午後、樹下美術館を訪ねて熱心に展示を見てくれた。5年前の時、私がここに美術館を建てたいと言ったのを覚えていて驚いた。たくましく成長していたが、優しさは変わりなかった。
今回、夕食は直江津の知人宅でお世話になった。夕陽を見ながら心ゆくまで楽しい夜をすごさせて頂いた。
ホームステイといえば、10年前にはニュージーランドの高校生を3ヶ月ほど預かった。彼は吉川高校へ通って、放課後には剣道に精進した。帰国後、彼も再来日し、ついには日本で日本人と結婚して可愛い子どもにも恵まれている。
二人とも個性的で心ひろやか、時折真っすぐな道徳の芯を見ることがあった。彼らの果敢な交流には平和への一灯として十分な意義がある。また斯く交流は、何かと排他的で硬い政治の下では為し難いものとして写る。若き日の頸北の一年、何かが彼らを惹き付けたにちがいない。
- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔
- 樹下だより
- 齋藤三郎(陶齋)
- 倉石隆
- 小山作之助・夏は来ぬ
- 聴老(お年寄り&昔の話)
- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス
- 花鳥・庭・生き物
- 空・海・気象
- 頸城野点景
- ほくほく線電車&乗り物
- 社会・政治・環境
- 明け暮れ 我が家 お出かけ
- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ
- 食・飲・茶・器
- 拙(歌、句、文)
- こども
- 館長の作品。
- 今年も咲いたカラタチの花。
- のどかな山桜、足許のすみれ草。
- 三冊の図書。
- 強風の日。
- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。
- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。
- 居ながらの花見 スミレの好意。
- 良いご一家の話。
- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。
- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。
- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。
- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。
- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。
- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。
- 自然の末席で。
- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。
- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。
- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。
- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。
- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月